今回ご紹介する本は、
『個性を輝かせる子育て、つぶす子育て』
です。
悩みがつきない【子育て】ですが、
本書を読むと
子供が個性豊かに自分らしく成長するには
親がどのように子供に接すればいいか?
親がどのような声掛けをすればいいか?
が分かります。
大谷翔平さんや藤井聡太さんの両親にも共通する子供への向き合い方も紹介されています。
◎こんな人におすすめ
・子供に対していつも怒ってばかり…
・子供へどんな声掛けをすればいいのか分からない
・思い通りに子供が育ってくれない
このような方はぜひ本書を手に取ってみてください。
『個性を輝かせる子育て、つぶす子育て』
タイトル:『メンタルドクターが教える 個性を輝かせる子育て、つぶす子育て』
著者:辻 秀一
出版社:フォレスト出版
【要約】

著者の辻秀一さんはスポーツメンタルドクターや産業医として活躍されている方です。
スポーツ医学、脳科学、心理学などを学んできてスポーツ選手の精神的なサポートをしてきた経験と
著者が実際に自分の子供を育てた経験。
それらを「子育て」に活かせるようにまとめたのが本書というわけです。
それでは本書の内容を大きく3つのポイントに絞ってまとめていきます。
個性を輝かせる子育てをするには…?
①個性は「マーケティング」ではなく「アート」
②大切なのは「目標」ではなく「目的」
③子供に伝えるのは「やり方」ではなく「あり方」
それぞれ解説していきます。
①個性は「マーケティング」ではなく「アート」

個性を輝かせるための子育て1つ目のポイントは、
「マーケティング的子育て」ではなく、「アート的子育て」を目指そうということです。
マーケティングとアート
マーケティングとは・・・その商品が売れるように市場の調査やお客さんのニーズなどを分析して販売戦略を考えたりすること。
アートとは・・・自分が創りたい作品を自分の意志で創ること。他者の分析などはしない。
子育てにおいても個性を輝かせるには、
周りと比べて、評価を気にして、親の価値観で育てる「マーケティング的子育て」ではなく、
外的な評価などは関係なく、存在そのものに価値がある「アート的子育て」を心がけることが個性を輝かせることにつながっていきます。
親の価値観
そもそも子育ての主役はあなた(親)ではなく、子供です。
親の価値感に当てはめて子供に接していくのではなく、子供も1人の人間として接していくことが大切です。
簡単そうですが、なかなか難しいことですよね。。。
たとえばこんな声を子供にかけていませんか?
「こっちのほうがいいよ!だから、パパとママの言うこと聞いて!」
もう我が家ではあるあるの声がけになっています。
子供の選択を聞かずに「こっちがいい」って親が決めてますよね。
これ完全に親の価値観を子供に押し付けてるだけかもしれません。
ではなく、
「あたなはどう思うの?あたなが決めたことだから応援するよ!」
このように子供が感じたままに子供が決める。
こんなスタンスが大切です。
超一流の親はどのように子供を育てたのか?
ちなみに現在、『一流』と言われ活躍している大谷翔平さんや藤井聡太さん。
大谷翔平さんのご両親が心がけていたことは、「頭ごなしに怒らない」「子供の考えを否定しない」
藤井聡太さんのご両親が心がけていたことは、「子供が集中しているときは絶対に止めない」
どちらも子供を1人の人間として信じているし、応援して、待つ。というアート的な子育てになっています。
②大切なのは「目標」ではなく「目的」

個性を輝かせるための子育て2つ目のポイントは、
「目標」ではなく、「目的」を大切にするということです。
まずは子育ての目的を考えてみる
【なぜ子育てをするのか?】という正解が見つかりにくい問いに対してまずは向き合うことが大切です。
親がこのような非認知的な思考を持つことでそのような価値観やものの見方が子供にも伝わり子供の思考に影響することになるからです。
ちなみに本書の著者にとって子育ての目的とは、
『自分自身に向き合い、主体的に生きていくための非認知的な脳を育むこと』
と書かれています。
もちろんこれが正解とか、こうなるべきということではなくて自分なりの子育ての目的を考えることが大切です。
「目標」で子育てすると苦しくなる
目標設定して、目標に向かって努力し、目標達成する。
これは世の中においてとても大事なことですが、
「目標を達成すること」ばかりを重要視すると苦しくなり、やる気の限界がきます。
目標とはあくまでも外部の基準だからです。
たとえば、
・テストで100点を取る
・試合で優勝する
など【外部からの評価】や相手がいることなので【比較】をしてしまいます。
一つの指標としてはとても大切なのですが目標達成に捉われると外部に振り回され、自分を見失ってしまいます。
そこで「目標」より「目的」の意識を持たせるようにしましょう。
・なぜテストで100点を取りたいの?
・なぜ試合で優勝したいの?
このように「なぜ?」を問いかければ、「目的」はなにかを考えることになります。
たとえば、
①困っている人を助けたい、役に立ちたい
②そのために看護師になりたい
③看護師になるための学校に行きたい
④だから今はテストで100点を目指して頑張る
目的がはっきりすれば子供自身の内側からのエネルギーとなります。内発的な動機となり主体的に行動する人間になっていくでしょう。
「テストでの100点」はあくまでも目的のための手段であり、プロセスとなります。
AI時代には非認知能力が不可欠
認知能力とは・・・知識、計算力などの学力のことで、点数や数値で表せる定量的な能力です。
非認知能力とは・・・自分らしさ、協調性、忍耐力など数値では表しにくい非定量的な能力です。
知識、計算力、記憶力などにおいては人間はAIには敵わないですよね。そこはAIに任せておける。
でもこんな時代だからこそ非認知能力が必要です。
自分の感情、自分の好きなこと、なぜ?と問う力、自分を信じる力。
こんな能力が私たち人間がこれからのAI時代を生き抜いていくためには必要です。
③子供に伝えるのは「やり方」ではなく「あり方」

個性を輝かせるための子育て3つ目のポイントは
子供には「やり方」ではなく、「あり方」を伝えるということです。
まずは親の心を整えること
親は子供に「やり方」を教えようとします。
できるのが、良い。 できないのは、ダメ。
周りのみんなができているから、うちの子もできないといけない。
やり方は外的なこと、つまり社会的な尺度が基準となっている場合が多いです。
そうではなく、「やり方」を教える前に「あり方」を伝えます。
「あり方」とは、「自分はどんな人間でありたいか?」です。
だから子供にあり方を伝えるにはまずは親が一人の人間としてどんな人間でありたいのか?という問いに向き合い親自身の心や思考を整える必要があります。
それでいて、はじめて子供と一緒に考え、伝えることができると思います。
自分で考えて、自分で気持ちを整理して、自分でやり方を見つけてチャレンジする姿勢。
主体的に行動していく姿勢。
誠実な姿勢。
これらのほうが大切にしたい人としてのあり方だと思います。
「結果」でなく「一生懸命」をほめる
・テストで100点を取れたらほめる。
・試合で勝ったらほめる。
これらは「結果」です。
あくまでも外的な評価や相手がいることです。どうしても自分自身だけではコントロールできない部分もありますよね。
でも「一生懸命に取り組んだこと」をほめるとどうでしょうか?
一生懸命に取り組むかどうかは自分でコントロールできますよね。
なにかに取り組む姿勢やプロセスに着目してあげれば、たとえテストの点数が60点でも、試合に負けても結果は関係ないですよね。
むしろもっと自分が好きなことに主体的に取り組んでいくのではないしょうか?
大切なのは「自己肯定感」より「自己存在感」
よく耳にする自己肯定感。
肯定するということはこれもなにか外的な評価や比較が関係していることが多いです。
・低いのはダメで、高いのが良い。
・遅いのはダメで、速いのが良い。
・できないのはダメで、できるのが良い。
どうしても比較になってしまいます。
このまま大人になると自分を見失い、周囲との比較を気にして常に社会的な結果を出し続けなくてはならないプレッシャーで苦しい人生になってしまいます。
それよりも「自己存在感」という考え方を持っておくことです。
自己存在感とは・・・自分の中に【ある】ものを意識していく考え方です。自分の存在がある、命がある。ということ。
赤ちゃんとして生まれてきたときはただそれだけで感謝していたはずなのに、成長するにつれてなぜか周りと比べたり、点数をつけたりして周囲より劣っていると指摘してしまいます。
子供に対して常に感謝の気持ち、ありのままを理解してあげることが親としては大切なことです。
【感想】

私自身も2人の子供を育てているパパですが、子育てはなかなかうまくいかないことも多くてついイライラしてしまったりということもあります。
・言うことを聞かない
・ごはん食べない
・歯磨きしない
・着替えない
などあげればキリがないですが日々苦戦しながらの子育てです。
でも本書を読んで反射的に注意したり、すぐに親が手伝ってしまう前に一旦立ち止まってまずは子供の気持ちを理解しようと心がけています。
たとえば、【ごはんを食べないとき】
お子さんがいる家庭ならあるあるだと思いますが、なかなかごはんを食べてくれない。
声掛けを少し変えてみました。
「早く全部食べて!なんで食べないの!」
→「自分のペースでいいんだよ。お!一口食べれたじゃん!」
実際このような声掛けに変えてみたら、二口目も食べて、お!2回食べた!というと3回、4回、5回とどんどん食べてくれた経験がありました。
子供には子供のペースが、子供には子供の考えがあるのでそれを理解して応援してあげることが大切だと感じました。
しかしそのためには、親の「あり方」が必要ですね。
日々忙しく過ぎていく中で子供が夢中になっているものを「見守る」「待つ」という時間と心の余裕。
親の価値観や世間の当たり前を強要していないかを常に意識していく必要があります。
【行動】

本書を読んで行動にしていくことをまとめていきます。
〇子育ての目的を考える
→ 子供を主体的に自分らしく幸せな人生を送ることができる人間に育てるため
〇声掛けを変えてみる
→目標ではなく「なぜ?」という目的の意識。
たとえば、「なぜそれができるようになりたいの?」「なぜ優勝したいと思ったの?」という声掛け。
→結果を褒めるのではなく、プロセスや取り組む姿勢にフォーカスする
たとえば、「一生懸命取り組んだことが素晴らしいね!」という声掛け。
【まとめ】
『個性を輝かせる子育て、つぶす子育て』の要約、感想をまとめました。
子育てには正解がなく、子供が何人いても同じ育て方で同じ人間に育つということはありません。
だからこそ、子供の成長と同時に親も子育てを通して成長できると思います。
まずは親がどんな人間でありたいか、そして子供をどんな人間に育てたいのかという目的をしっかりと持つことが大切です。
子供に自分らしく生き抜いてほしい。そんな個性を輝かせる子育てに共感できた方はぜひ実際に本書を手に取って読んでみてください。
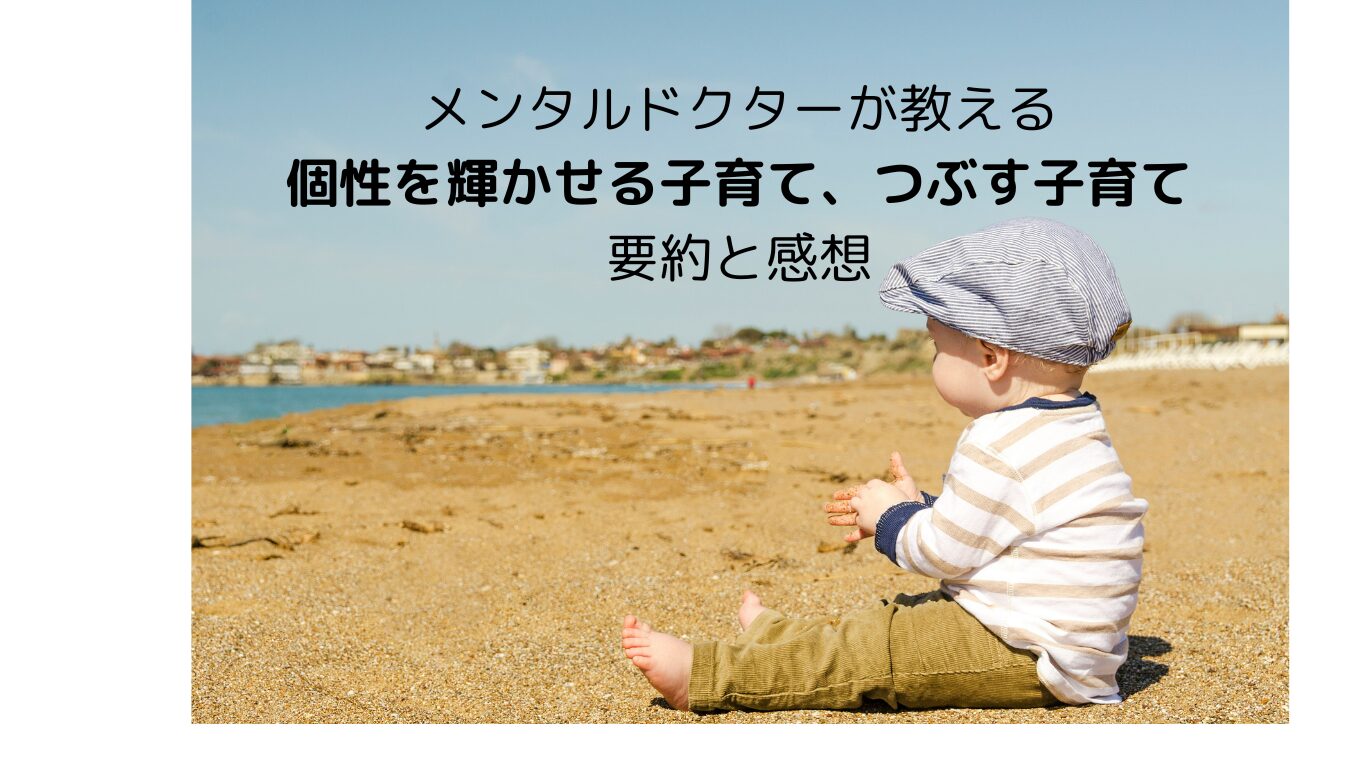


コメント